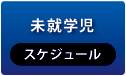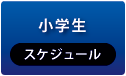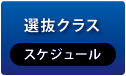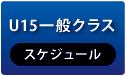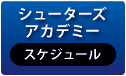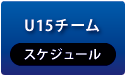鎌ケ谷市 白井市 船橋市 八千代市 松戸市 柏市 八千代市 印西市 習志野市 ミニバス バスケ
Blog
2025年11月26日 [バスケットボール]
えっ、大丈夫?? 転んでも手が付けない・・・ 運動する基礎が正しくできていない子供たちが急増・・・
昨今、子どもたちの運動能力低下が社会問題になっています。
それは、昔と比べて公園遊び等の機会が減り、子供たち同士での「遊び時間」「遊び場所」「遊び仲間」という環境が大きく変化しています。
ゲーム・携帯電話などインドアで遊ぶ道具類が増え、スマホ一つで友達とオンラインゲームができる便利さがある一方で、公園の外遊びは大幅に減っています。
さらに場所的な制約もあります。昔は縄跳びやボールなど一つあれば広場などで野球などができましたが、現在は公園でのボール使用が禁止されているケースも多く制約が実に多いです。
こうした要因が重なり、文部科学省での発表による学校の体力測定でも子供たちの年齢に見る数値の大幅な低下が見られています。
最近よく耳にする大きな出来事は、
「転んだ時に手がつけなくて、顔から突っ込んでしまう子がいる・・・」
という大変ショッキングな話を聞いて驚きました。
様々な動きを経験していない子が増えていることは、当クラブ・PBAバスケットボール・スクールで接する子どもたちからの様子からも実感します。
その大前提となる運動能力、さらには姿勢や走り方、腕の振りなどが正しくできない中で、スポーツ・バスケットボールのスキルトレーニングばかりしていても、はたして上達するのだろうか・・・?
と思います。
人のカラダはトレーニングしたことに順応し、適応します。
瞬発力を上げるためには、瞬発力向上のためのトレーニングが不可欠です。
バスケットボールをプレーする中で、「瞬発力がない」「速く走れない」「うまくターンできない」といった課題があれば、その部分を徹底的にトレーニングするしかありません。
今の子どもたちは外遊びや運動の機会が大幅に減少していて、特にコロナ禍を経て、運動能力の低下を肌で感じます。
今まで見られなかった動きや「どうしてそうなっちゃうの?」と思うような状況も増えています。それでもバスケットボールのトレーニングだけで、バスケットボールを上手くしようとしている。
そこが重要なポイントで、走る、止まる、投げるという動きも、バスケットボールの技術の一つとして捉えてほしい。そして、そのためのトレーニングをすることで、うまくいかない状況を改善するという考え方を持ってもらえると、子どもたちの成長につながるのではないでしょうか。
びっくりする・・・ 二極化する子どもたちの運動能力 バスケットボールの現場で今・・・
PBAバスケットボール・スクールで子どもたちの様子を見ていると、いろいろな動きや遊びを経験している子は、鬼ごっこでも身体が素早く反応し、相手の動きを予測して逆を取るような動きができます。一方で苦手な子はずっと鬼のままの状況や、そもそも「鬼ごっこは嫌だ・・・」と言うこともあります。
バスケットボールにおいても二極化が進んでいて、熱心に取り組む子とただなんとなくの感覚でやる子に分かれています。後者は自己肯定感が低く、可能性を狭めてしまっているケースが多いです。
また、親が短絡的・短期的な視点で我が子を直ぐに見区切り、辞めさせてしまうことも大きな原因の一つです。
これは大きな問題だと感じています。
運動に苦手意識を持つ子たちには「こう動かすといいよ」というアドバイスを通じて「こうすればいいんだ」「前より上手にできた」という成功体験が必要です。
それは、体の動かし方のプロから指導を受けることや、我々指導者が知識を身につけて、正しく指導することの重要性を痛感しています。
そうすることで、子どもたちの苦手意識が少しでも解消され、自己肯定感が高まり、チャレンジ精神や「もっと良くなるにはどうしたらいいだろう」という探究心が生まれるきっかけになればと思います。
そして、それがスポーツ・バスケットボールだけではなく、勉強や日常生活へイキイキと取り組むことへの活発性へと繋がっていくのです。
PBAバスケットボール・スクールを通して、子どもの自己肯定感を高め自信がつき、スポーツ全般の記録が伸びた子も!!
自己肯定感は子どもに不可欠なもので、人を大きく変えることがあります。
これは、幼少期であればあるほど、脳やカラダに浸透し、学習能力としてインプットされ、後の高校〜大学〜社会人となっても、必ず活きていきます!!
以前、PBAのバスケットボール・スクールに来た男の子で、バランス感覚が悪く、走る時に右手と右足を同時に動かして走ってしまう・・・という子がいました。
初めは「この子、大丈夫かな」と思ったのですが、勘が良かったのか、たった1回のトレーニングで何かをつかんだようで動きが変わり、家に帰ってから自主練習をするようになったそうです。
その結果、最初は自信がなく消極的だった子が、スピードが上がってくると表情が変わり、自分から話しかけるようになってきたのです。お母さんも「性格が変わってしまったみたい」と驚いていました。
それは、「探究心」が一つのキーワードになっています。
自分で考えて取り組んでうまくいったとき、さらに「どうすれば良いだろう?」と興味を持つもの。
子どものそのパワーは本当にすごいと思います。
バスケットボールの目先のスキル習得の前に、自分で体を動かすことが好きになり、得意になることで探究心が生まれてくる、ここがとても大切だと思います。
身体を適切に動かすことができるとスポーツ・バスケットボールのパフォーマンスが変わる
親の決めつけや、子供の引っ込み思案な考えの、「やったことないからできない」「やる前からできない」「どうせ自分なんて......」と思っている子は実は多いですよね。
それは、子供自身がそのようになるのではなく、親を含めた自己肯定感を高めること、経験値・体験をさせてこなかった親に問題・課題の多くはあるのですよね、実は・・・
よって、PBAバスケットボール・スクールは、初めは
「カラダを適切な動きを通して、動かすことが楽しいね」
「自信を持って、自分の得意なプレーからしていいよ」
というところから始めます。
「できたね、そこがすごいね」
と認めてあげると、さらに自己肯定感が高まって伸びていきます。
現状の環境はすぐには変えられません・・・
公園に遊具を増やしたり、ボール遊びOKにするのは簡単ではありません。
その中で、PBAバスケットボール・スクールの指導者は子どもたちにとって、どうすればより良い環境を作ってあげられるかを考えることがとても大切だ・・・と思っています。
子供にとって健康な食生活を送るうえでの運動習慣、その第一歩がPBAバスケットボール・スクールであることを今も、今後も引き続き提供していきたいと強く思っております。
それは、昔と比べて公園遊び等の機会が減り、子供たち同士での「遊び時間」「遊び場所」「遊び仲間」という環境が大きく変化しています。
ゲーム・携帯電話などインドアで遊ぶ道具類が増え、スマホ一つで友達とオンラインゲームができる便利さがある一方で、公園の外遊びは大幅に減っています。
さらに場所的な制約もあります。昔は縄跳びやボールなど一つあれば広場などで野球などができましたが、現在は公園でのボール使用が禁止されているケースも多く制約が実に多いです。
こうした要因が重なり、文部科学省での発表による学校の体力測定でも子供たちの年齢に見る数値の大幅な低下が見られています。
最近よく耳にする大きな出来事は、
「転んだ時に手がつけなくて、顔から突っ込んでしまう子がいる・・・」
という大変ショッキングな話を聞いて驚きました。
様々な動きを経験していない子が増えていることは、当クラブ・PBAバスケットボール・スクールで接する子どもたちからの様子からも実感します。
その大前提となる運動能力、さらには姿勢や走り方、腕の振りなどが正しくできない中で、スポーツ・バスケットボールのスキルトレーニングばかりしていても、はたして上達するのだろうか・・・?
と思います。
人のカラダはトレーニングしたことに順応し、適応します。
瞬発力を上げるためには、瞬発力向上のためのトレーニングが不可欠です。
バスケットボールをプレーする中で、「瞬発力がない」「速く走れない」「うまくターンできない」といった課題があれば、その部分を徹底的にトレーニングするしかありません。
今の子どもたちは外遊びや運動の機会が大幅に減少していて、特にコロナ禍を経て、運動能力の低下を肌で感じます。
今まで見られなかった動きや「どうしてそうなっちゃうの?」と思うような状況も増えています。それでもバスケットボールのトレーニングだけで、バスケットボールを上手くしようとしている。
そこが重要なポイントで、走る、止まる、投げるという動きも、バスケットボールの技術の一つとして捉えてほしい。そして、そのためのトレーニングをすることで、うまくいかない状況を改善するという考え方を持ってもらえると、子どもたちの成長につながるのではないでしょうか。
びっくりする・・・ 二極化する子どもたちの運動能力 バスケットボールの現場で今・・・
PBAバスケットボール・スクールで子どもたちの様子を見ていると、いろいろな動きや遊びを経験している子は、鬼ごっこでも身体が素早く反応し、相手の動きを予測して逆を取るような動きができます。一方で苦手な子はずっと鬼のままの状況や、そもそも「鬼ごっこは嫌だ・・・」と言うこともあります。
バスケットボールにおいても二極化が進んでいて、熱心に取り組む子とただなんとなくの感覚でやる子に分かれています。後者は自己肯定感が低く、可能性を狭めてしまっているケースが多いです。
また、親が短絡的・短期的な視点で我が子を直ぐに見区切り、辞めさせてしまうことも大きな原因の一つです。
これは大きな問題だと感じています。
運動に苦手意識を持つ子たちには「こう動かすといいよ」というアドバイスを通じて「こうすればいいんだ」「前より上手にできた」という成功体験が必要です。
それは、体の動かし方のプロから指導を受けることや、我々指導者が知識を身につけて、正しく指導することの重要性を痛感しています。
そうすることで、子どもたちの苦手意識が少しでも解消され、自己肯定感が高まり、チャレンジ精神や「もっと良くなるにはどうしたらいいだろう」という探究心が生まれるきっかけになればと思います。
そして、それがスポーツ・バスケットボールだけではなく、勉強や日常生活へイキイキと取り組むことへの活発性へと繋がっていくのです。
PBAバスケットボール・スクールを通して、子どもの自己肯定感を高め自信がつき、スポーツ全般の記録が伸びた子も!!
自己肯定感は子どもに不可欠なもので、人を大きく変えることがあります。
これは、幼少期であればあるほど、脳やカラダに浸透し、学習能力としてインプットされ、後の高校〜大学〜社会人となっても、必ず活きていきます!!
以前、PBAのバスケットボール・スクールに来た男の子で、バランス感覚が悪く、走る時に右手と右足を同時に動かして走ってしまう・・・という子がいました。
初めは「この子、大丈夫かな」と思ったのですが、勘が良かったのか、たった1回のトレーニングで何かをつかんだようで動きが変わり、家に帰ってから自主練習をするようになったそうです。
その結果、最初は自信がなく消極的だった子が、スピードが上がってくると表情が変わり、自分から話しかけるようになってきたのです。お母さんも「性格が変わってしまったみたい」と驚いていました。
それは、「探究心」が一つのキーワードになっています。
自分で考えて取り組んでうまくいったとき、さらに「どうすれば良いだろう?」と興味を持つもの。
子どものそのパワーは本当にすごいと思います。
バスケットボールの目先のスキル習得の前に、自分で体を動かすことが好きになり、得意になることで探究心が生まれてくる、ここがとても大切だと思います。
身体を適切に動かすことができるとスポーツ・バスケットボールのパフォーマンスが変わる
親の決めつけや、子供の引っ込み思案な考えの、「やったことないからできない」「やる前からできない」「どうせ自分なんて......」と思っている子は実は多いですよね。
それは、子供自身がそのようになるのではなく、親を含めた自己肯定感を高めること、経験値・体験をさせてこなかった親に問題・課題の多くはあるのですよね、実は・・・
よって、PBAバスケットボール・スクールは、初めは
「カラダを適切な動きを通して、動かすことが楽しいね」
「自信を持って、自分の得意なプレーからしていいよ」
というところから始めます。
「できたね、そこがすごいね」
と認めてあげると、さらに自己肯定感が高まって伸びていきます。
現状の環境はすぐには変えられません・・・
公園に遊具を増やしたり、ボール遊びOKにするのは簡単ではありません。
その中で、PBAバスケットボール・スクールの指導者は子どもたちにとって、どうすればより良い環境を作ってあげられるかを考えることがとても大切だ・・・と思っています。
子供にとって健康な食生活を送るうえでの運動習慣、その第一歩がPBAバスケットボール・スクールであることを今も、今後も引き続き提供していきたいと強く思っております。