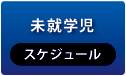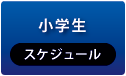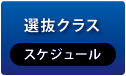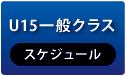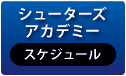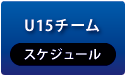鎌ケ谷市 白井市 船橋市 八千代市 松戸市 柏市 八千代市 印西市 習志野市 ミニバス バスケ
Blog
2025年11月27日 [バスケットボール]
子供が自信を持つ方法、それは・・・
最近、多くの質問にて、
「うちの子は自信をもってプレイしてなんですよね・・・」
と耳にする。
自信は高いパフォーマンスを生む要素のひとつであり、バスケットボールを楽しんでプレーするという部分にもつながっていきます。
逆に自信がなければ、思い切ったプレーができず、バスケットボールそのものが嫌いになっていく可能性もあります。
では、自信につながることとは何でしょうか?
自信は成功体験を重ねるなかで身に付いていきます。
ただし、その成功体験のすべてが自信につながるわけではありません。
成功体験には2つの種類があり、その違いが自信につながるか、そうではないかの分岐点になります。
端的に申せば、子供・選手が目の前の問題・課題に対して、
●与えられた課題をこなす・・・
なのか、
◎自身で率先して見出し、トライアウンドエラーを繰り返して自主的に考え取り組む・・・
かなのです。
与えられた課題に取り組むという外発的動機付けで動くのか、自ら課題に気づき挑戦しようという内発的動機付けのやる気を導き出すことが、自信を得るための近道ということです。
大切なのは仮説を持たせること!!
『これをやって』ではなく、『これをやれば、どうなると思う?』という投げかけです。
そのうえで取り組めば、『どうなるんだろう?』という答えを模索しながら、成功体験に向かうことになります。
そうなると、できたときの喜びが大きくなり、更なる内発的動機付けが出来て、それがスポーツ・バスケットボールのみならず、その思考がその子の行動特性へと活きてくるわけです。
それって、勉強も同じ思考・サイクルなので、勉強ができる頭の良し悪しの思考・サイクルって、幼少期のこの成功体験に基づく行動特性となるのを分かっている親と分からずの親の元で育つ家庭環境での子供の学力に差が生じてくるのですよね、実は・・・
自信の構成要素は以下の3つに分類されます。
1.結果・勝利・高評価
2.「心・技・体」それぞれの能力・長所・武器
3.トレーニング時間・家庭生活・日常生活・努力・工夫・気づき
そしてより求められるのは、2と3になります。
このふたつは自分自身の準備からくる自信です。
子どもの試合を見ていると、ミスをしたとたんに急にシュンとなって落ち込んだりすることがよくあると思います。それはミスしたことによって、結果による自信がなくなります。
普段も結果や勝利、プレーに対する高評価からしか自信を得られていないため、ミスした瞬間に、『どうしよう、評価が下がってしまう』と周りの目ばかり捉え考えてしまいます。
でも、実際にはミスをしても培ってきた技術の質が落ちるわけではありません。
だからこそ、準備からくる自信を構築することが大切になってきます。
長所・武器を活かすことと努力や工夫の要素を重視するには、指導者、保護者の声かけやサポート、褒め方を含めたフィードバックが大事になります。
ただ、そのフィードバックには、しっかりとしたフィードフォワード(事前の予測・イメージ・目標設定や仮説へチャレンジする気持ち)がなければいけません。
フィードバックはできたかできなかったという結果に対してのものではなくて、
なにが良くて、何がダメだったのかということ・・・
を、子どもたちと一緒に探ることが必要です。
そして、そのチャレンジや努力のプロセスを褒めることが自己肯定感が高まり、次への行動への子供・選手のモチベーションにつながることにてとても大切です。
試合に勝つことだけでは自信を得ることはできない・・・
自信を植え付けるには、勝つことだけでは意味がない。
そこに意義を持たせないといけません。
意義とは、具体的に言えば実力発揮になります。
準備を大切にして、実力発揮をする可能性を高めて試合に臨む。
それによって得た結果は、勝とうが負けようが、必ず自信につながります。
大切なのは長期的な視点に立ち、子どもたちの成長、進化を促してしていくことです。
結果ではなく、そこに向かうチャレンジやプロセスに評価の基準を置き、フィードフォワードとフィードバックをしていくことです。
ミスを起きたときは自信が低下しているかというと、必ずしもそうではありません。
ミスからの切り替えの早い選手は、そのあとに何をするかのイメージや修正に集中するわけです。
逆にそうではない選手は、ミスが起きたことにより評価が下がるイメージや、味方に何かを言われるんじゃないかというマイナスイメージが働いてしまうのです。
ですから、集中の向け先を変えるような声かけをすることです。
『次の準備をしよう』
『次に何が起きそうかを考えよう』
など、起きたことではなく、これから起きることにイメージを持っていくことをおすすめします。
逆に怒ったり、怒鳴ったりするのはマイナスイメージにさらに拍車をかけてしまうことになります。
怒られれば、悪いイメージを作り出してしまいます。
それは試合中に必要のないことなのです。
やはり、指導者は感情をコントロールすべきです。
怒鳴っていいことなんて、なにひとつありませんので・・・
PBAでは、子供・選手へ自信を持ってプレーをしてほしく、子供・選手のチャレンジや工夫などプロセスを評価し、子どもがミスをしても前向きになれるような声かけをすることを心がけております。
それは、小学生・中学生の時期が選手の完成形ではないからです。
また、この小中学生の時期に育んだ・培った思考・行動特性は、子供達がのちの高校・大学・社会人となったときに同じ思考・行動特性で高いパフォーマンスをする自信のもった人となることへの育成の環境ステージと捉えているからです。
勉強で頭がよくなる・成績が良くなるには、机に向かって勉強するだけではダメなんです・・・(笑)
その勉強をするための思考・行動特性をあらゆる場面、その一つがスポーツ・バスケットボールであり、数多くあるバスケットボールのチーム・スクールの中でも、それを理解して取り組んでいるクラブがPBAであること・・・
PBAは大切なお子様の成長をサポートして参ります。
「うちの子は自信をもってプレイしてなんですよね・・・」
と耳にする。
自信は高いパフォーマンスを生む要素のひとつであり、バスケットボールを楽しんでプレーするという部分にもつながっていきます。
逆に自信がなければ、思い切ったプレーができず、バスケットボールそのものが嫌いになっていく可能性もあります。
では、自信につながることとは何でしょうか?
自信は成功体験を重ねるなかで身に付いていきます。
ただし、その成功体験のすべてが自信につながるわけではありません。
成功体験には2つの種類があり、その違いが自信につながるか、そうではないかの分岐点になります。
端的に申せば、子供・選手が目の前の問題・課題に対して、
●与えられた課題をこなす・・・
なのか、
◎自身で率先して見出し、トライアウンドエラーを繰り返して自主的に考え取り組む・・・
かなのです。
与えられた課題に取り組むという外発的動機付けで動くのか、自ら課題に気づき挑戦しようという内発的動機付けのやる気を導き出すことが、自信を得るための近道ということです。
大切なのは仮説を持たせること!!
『これをやって』ではなく、『これをやれば、どうなると思う?』という投げかけです。
そのうえで取り組めば、『どうなるんだろう?』という答えを模索しながら、成功体験に向かうことになります。
そうなると、できたときの喜びが大きくなり、更なる内発的動機付けが出来て、それがスポーツ・バスケットボールのみならず、その思考がその子の行動特性へと活きてくるわけです。
それって、勉強も同じ思考・サイクルなので、勉強ができる頭の良し悪しの思考・サイクルって、幼少期のこの成功体験に基づく行動特性となるのを分かっている親と分からずの親の元で育つ家庭環境での子供の学力に差が生じてくるのですよね、実は・・・
自信の構成要素は以下の3つに分類されます。
1.結果・勝利・高評価
2.「心・技・体」それぞれの能力・長所・武器
3.トレーニング時間・家庭生活・日常生活・努力・工夫・気づき
そしてより求められるのは、2と3になります。
このふたつは自分自身の準備からくる自信です。
子どもの試合を見ていると、ミスをしたとたんに急にシュンとなって落ち込んだりすることがよくあると思います。それはミスしたことによって、結果による自信がなくなります。
普段も結果や勝利、プレーに対する高評価からしか自信を得られていないため、ミスした瞬間に、『どうしよう、評価が下がってしまう』と周りの目ばかり捉え考えてしまいます。
でも、実際にはミスをしても培ってきた技術の質が落ちるわけではありません。
だからこそ、準備からくる自信を構築することが大切になってきます。
長所・武器を活かすことと努力や工夫の要素を重視するには、指導者、保護者の声かけやサポート、褒め方を含めたフィードバックが大事になります。
ただ、そのフィードバックには、しっかりとしたフィードフォワード(事前の予測・イメージ・目標設定や仮説へチャレンジする気持ち)がなければいけません。
フィードバックはできたかできなかったという結果に対してのものではなくて、
なにが良くて、何がダメだったのかということ・・・
を、子どもたちと一緒に探ることが必要です。
そして、そのチャレンジや努力のプロセスを褒めることが自己肯定感が高まり、次への行動への子供・選手のモチベーションにつながることにてとても大切です。
試合に勝つことだけでは自信を得ることはできない・・・
自信を植え付けるには、勝つことだけでは意味がない。
そこに意義を持たせないといけません。
意義とは、具体的に言えば実力発揮になります。
準備を大切にして、実力発揮をする可能性を高めて試合に臨む。
それによって得た結果は、勝とうが負けようが、必ず自信につながります。
大切なのは長期的な視点に立ち、子どもたちの成長、進化を促してしていくことです。
結果ではなく、そこに向かうチャレンジやプロセスに評価の基準を置き、フィードフォワードとフィードバックをしていくことです。
ミスを起きたときは自信が低下しているかというと、必ずしもそうではありません。
ミスからの切り替えの早い選手は、そのあとに何をするかのイメージや修正に集中するわけです。
逆にそうではない選手は、ミスが起きたことにより評価が下がるイメージや、味方に何かを言われるんじゃないかというマイナスイメージが働いてしまうのです。
ですから、集中の向け先を変えるような声かけをすることです。
『次の準備をしよう』
『次に何が起きそうかを考えよう』
など、起きたことではなく、これから起きることにイメージを持っていくことをおすすめします。
逆に怒ったり、怒鳴ったりするのはマイナスイメージにさらに拍車をかけてしまうことになります。
怒られれば、悪いイメージを作り出してしまいます。
それは試合中に必要のないことなのです。
やはり、指導者は感情をコントロールすべきです。
怒鳴っていいことなんて、なにひとつありませんので・・・
PBAでは、子供・選手へ自信を持ってプレーをしてほしく、子供・選手のチャレンジや工夫などプロセスを評価し、子どもがミスをしても前向きになれるような声かけをすることを心がけております。
それは、小学生・中学生の時期が選手の完成形ではないからです。
また、この小中学生の時期に育んだ・培った思考・行動特性は、子供達がのちの高校・大学・社会人となったときに同じ思考・行動特性で高いパフォーマンスをする自信のもった人となることへの育成の環境ステージと捉えているからです。
勉強で頭がよくなる・成績が良くなるには、机に向かって勉強するだけではダメなんです・・・(笑)
その勉強をするための思考・行動特性をあらゆる場面、その一つがスポーツ・バスケットボールであり、数多くあるバスケットボールのチーム・スクールの中でも、それを理解して取り組んでいるクラブがPBAであること・・・
PBAは大切なお子様の成長をサポートして参ります。